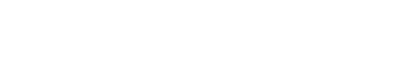申請の後にも前にも時間が必要となる 耐震基準適合証明書の発行までの基本的なフローは、図のような流れになっています。 まず第一に、耐震基準適合証明書は申請すればすぐに発行されるというものではなく、また必ず発行されるというもので[…]
1.国の文書では申請者は売主と明記
耐震基準適合証明書は中古住宅を購入した時に住宅ローン控除を受けるために必要になる書類です。しかし、この証明書の発行を申請できるのは原則として売主になっていて、減税を受ける買主ではありません。
耐震基準適合証明書の制度が出来たのは平成17年の税制改革においてです。当時国土交通省のHPにアップされていた税制改革概要には売主が依頼するものと明記されており、この制度の特長であることが分かります。

また国土交通省のHPには耐震基準適合証明書の記入例もアップされており、これにも申請者を売主とするようになっていました。

参考資料:国土交通省 耐震基準適合証明書記入例 全文(PDF)
この記入例は現在、売主との記載が消えています。このため制度が変更になったと勘違いする人もいますが、制度は変更になっていません。新しい制度が追加されたので、従来のものと兼ねた記入例になっただけです。
新しい制度では買主が申請して耐震基準適合証明書の発行を受けるものになっており、かつ証明書の様式が共通にされたため、記入例から売主という文字が消えたというに過ぎません。
追加された制度は、買主が物件の引渡し後に耐震改修工事をしてから耐震基準証明書の発行を受けるものです。ただし条件として、証明書の申請は引渡し前に行わればなりません。そのための申請書は法定の様式となっていて、それには申請人を買主とするようになっています。

参考資料:国交省 <要耐震改修住宅用>耐震基準適合証明申請書 全文(PDF)
この申請書と改修工事の請負契約書の写しを付け加えて確定申告を行うと、引渡しまでに証明書が発行されたものとみなされるのが新たに追加された制度です。従来からの制度は租税特別措置法第41条第1項の規定ですが、この制度は同法第41条第30項の規定となっていて、別制度であることが分かります。
したがって現在でも、耐震基準適合証明書の申請者は原則として売主であることは変わっていません。
2.減税は住宅耐震化へのインセンティヴ
耐震基準適合証明書の申請者が売主であることに疑問を感じる人は少なくありません。住宅ローン控除等の減税を受けるのは買主であるのに、ナゼ買主が申請できないのか?似たような名前のフラット35適合証明書では誰が申請してもいいのにおかしいではないか?といった疑問です。
確かに減税を受けるのは買主です。そもそも住宅ローン控除の目的は国民の住宅取得の促進であり、それによる経済活性化を狙っています。10年間で最大200万円もの減税は、住宅購入意欲を高めるためのインセンティヴ(奨励策)であり、それゆえ買主が減税の恩恵に預かれるようになっています。
この住宅ローン控除は、住宅ならどんな住宅を購入しても減税を受けられる訳ではありません。質の低い住宅を取得しても国民の生活の向上には繋がらないからです。このため床面積に一定以上の制限が設けられ、中古住宅においては一定の築年数(経過年数基準)以内の住宅に限られていました。
この築年数の制限に対して、それを超えた中古住宅であっても耐震性能が新築のものと同等のものは、質の高い住宅として住宅減税の対象に加えたのが平成17年の税制改革です。そしてその耐震性能を証明する書類として耐震基準適合証明書が制度化されたのです。
ただしこの制限緩和にも問題があり、それは耐震性の高い中古住宅をどうやって供給するかという問題です。いくら制限緩和をしたところで、該当する中古住宅が僅かしか存在ない確率の低いものであれば住宅取得の促進という政策目標は実現できません。
また我が国では憲法第84条によって租税法律主義を採っており、その機能である納税者による租税負担の予測可能性という面においても、減税が受けられるかどうかは買ってみなければ分からないというギャンブルのような状況は好ましくありません。
こうした状況を改善して耐震性の高い中古住宅をたくさん供給するためには、中古住宅の所有者の努力が不可欠になります。耐震性能が不足している住宅は耐震改修工事を施し、耐震性能を満たした住宅に対してはその性能が維持できるように適切にメンテナンスを行うことが必要になります。
所有者による住宅耐震化の努力を促すためにはインセンティヴが必要となります。すなわち耐震化により所有する住宅の資産価値が高まるようにすることです。住宅減税の対象となることは資産の高付加価値化に相当します。これをインセンティヴとして用いるためには、努力をした所有者が耐震基準適合証明書の申請者となるのが効果的といえます。
なお所有者へのインセンティヴとしての機能を重視するのであれば、耐震基準適合証明書の発行期限は売買契約までにする方がより効果的であり、また買主の租税負担の予測可能性という点でも問題ないのですが、現在の税制では引渡しまでと長くなっています。築年数の算定基準が引渡しであることに合わせているなどが理由と考えられます。
売買契約の後に調査をすることは可能にはなっていますが、減税の可否という資産価値が不明なままに契約をすることは価格の妥当性に不透明さが残ることになり、売主にとっても買主にとっても好ましいことではありません。
3.耐震基準適合証明書は租税法による規定
耐震基準適合証明書の法的な位置付けを確認してみましょう。証明に用いられる耐震診断について定めているのは耐震改修促進法になります。
耐震改修促進法は、建築物の地震に対する安全性の向上を図ることを目的とした法律です。耐震改修の基本方針や耐震診断の指針を定めており、また建築物の所有者に耐震診断の義務付けや指導、指示を行うことが出来るようになっています。
耐震基準適合証明書が出来たのと同じ平成17年には耐震改修促進法が改正され、建築物の所有者に対する指導等が強化されました。また建築物の所有者への支援として、所有者が行う耐震診断への補助金制度が各自治体によって創設されました。
このように所有者を耐震診断の実施者として施策を定めたのは、耐震改修工事を行うことが出来るのは所有者であり、その所有者が耐震診断を実施しなければ施策の実効性が乏しくなるためです。
それでは耐震改修促進法においては、耐震基準適合証明書の申請者についてどのように規定しているのでしょうか?実は何も規定していません。申請者についてだけでなく、耐震基準適合証明書のことは耐震改修促進法には何も書かれていないのです。これは意外に知られていない事実です。
一方、住宅ローン控除を定めている法律は租税特別措置法です。租税特別措置法では耐震基準に適合する中古住宅を減税の対象にすることを定めていますが、耐震基準に適合するかどうかの判定方法については耐震改修促進法に委ねた形になっており、耐震改修促進法において耐震診断の方法が定められています。
しかし耐震診断で判定を行って耐震基準に適合することが確認された後に作成される証明書については、元に戻って租税特別措置法の方で規定されているのです。いわば証明作業を耐震改修促進法に外注して、証明書作成は直営でやるような形になっており、耐震基準適合証明書の大きな特長といえます。
耐震基準適合証明書の代わりとして用いられることがある既存住宅性能評価書は、売主以外の申請が可能になっています。既存住宅性能評価書は住宅品質確保法により規定されていて、評価書の作成については租税特別措置法に影響されません。ここに大きな違いが出てくるのです。
4.売主申請は憲法からの制約
耐震基準適合証明書が耐震改修促進法ではなく租税特別措置法で規定されていることは大きな意味をもっています。それは法規の解釈において、拡張解釈が禁止されるということです。
租税特別措置法は租税法の一つであり、憲法第84条による租税法律主義から租税法では拡張解釈が原則禁じられる旨の最高裁判決がなされていて、文理解釈を用いなければならないのが原則とされています。
したがって耐震基準適合証明書の作成においては、文章の意味を文法の規則および通常の言葉の用法から確定する文理解釈によって法規を適用せねばなりません。これが想像以上に難しいのは、専門家特有の言葉の用法で解釈すると拡張解釈になってしまうからです。
例えば「家屋調査」という言葉に対して、専門家である建築士は、家屋そのものの調査は当然のこととして、家屋の設計図面の調査や、家屋の工事記録写真の調査もイメージします。またこれらの調査資料を用いて、構造計算等の解析作業を行い耐震診断することも調査業務と呼んでいます。しかしこれら全てを家屋調査と捉えると、租税法規では拡張解釈になってしまいます。
文理解釈では、「家屋調査」とは家屋そのものの調査のことです。家屋の設計図面の調査は、家屋ではなく図面の調査です。家屋の工事記録写真の調査は、家屋ではなく写真の調査となります。家屋の現地調査のみが「家屋調査」です。専門家としての常識をいったん捨て去らねばならないので、文理解釈は非常に難しいものとなります。
言い方を換えると、法規に書いてあるそのままのとおりに実行するということです。そしてこれはさらに重要な意味をもっています。書いてあるとおりに実行するということは、書いてないことは出来ないということです。また書いてあることはすべて意味があるということです。
租税特別措置法では耐震基準適合証明書の申請者についての条件を規定した条文はありません。このため誰でも自由に申請者になれると解釈する人がいますが、それは誤りです。法定の証明書様式に申請者欄が存在すること自体に意味があるからです。
もし耐震基準適合証明書の申請を誰でも出来るのであれば、証明書様式に申請者欄は不要です。耐震基準適合証明書は租税特別措置法により規定されたものなので、証明書全体が税務署の審査の対象になります。逆に審査に不要なものは様式制定の段階で外されています。申請者欄があるということは、申請者たるには何らかの制限があり審査対象であることを意味します。
所有者が申請者になれるのは当然ですが、他の者が申請者になるためにはその条件が必要です。最低限必要な条件は、所有者の財産権を侵さないことです。憲法第29条に財産権は侵してはならないと規定されています。
買主が申請しても売主の財産権を侵さないことを示す何らかの文書がエビデンスとして必要となります。例えば所有者からの同意書や委任状などです。しかし租税特別措置法ではそのエビデンスについても規定をしていません。
法定のエビデンスが規定されていなければ、所有者以外の者が申請してきても、その名を申請者欄に記載していいかどうかの判断が出来ないため証明書が作成できなくなります。
したがって所有者のみしか申請者となれず、耐震基準適合証明書は引渡し前に発行しなければならないので、建築士が受け付けられるのは原則として売主が申請者の場合のみということになります。(例外は事前に管轄税務署が認めた場合に限られます)
なお、買主が引渡し後に耐震改修をする制度では、エビデンスとして申請書の法定様式が規定されたことで、建築士は所有者でない買主の申請を受け付けられるようになりました。逆にこの法定申請書様式の存在により、証明申請者が売主に制限されている原則が明白に示されています。
耐震基準適合証明書と似たような書類として、フラット35適合証明書というものがありますが、こちらには証明書様式に「申請者欄」が存在しません。フラット35では申請者は誰でも可能となっており、それは様式の違いに表れているのです。
以上のように、憲法上から権利制限となるような直接的禁止規定は設けられていませんが、様式に「申請者欄」を設けて、申請者を審査対象とすることで間接的に所有者以外の申請を制限する形式をとっているという訳です。
また税務署が規定にないエビデンスを認める余地は残されていますが、これも憲法第84条の租税法律主義があるため慎重に判断されます。例外として事前に税務署の判断があれば、建築士が売主以外の申請を受け付けることは可能となっています。
「減税を受けるのは買主なのに不合理では?」という疑問は実は逆なのです。所有者である売主が申請するという前提の上で、減税を受ける買主を保護するために租税法律主義があり、耐震基準適合証明書の発行を物件の取得までに必要とされる制度にしているのです。あえて不合理な点をあげれば、取得の日を契約日ではなく引渡日で扱っている点だといえます。
[参考資料]
最高裁平成27年7月17日判決 判例タイムズ1418号(PDF)
最高裁昭和48年11月16日判決 民集27巻10号1333(PDF)
申請するかどうかは売主次第となっているので、耐震基準適合証明書の取得を後回しにすることは買主にとって大きなリスクとなります。証明書が取得できるかどうかの調査を契約等に先行して行うことが売主と買主の双方にとって大きなメリットとなります。先行調査に最適な適合証明調査業務については下記のページをご覧ください。
耐震基準適合証明書は、中古住宅で一定年数以上経過した物件にて、住宅ローン控除等の住宅減税を受けるために必要となるものです。しかし調査の結果次第では発行できないことがあるなどのため、その不確実性(ギャンブル性)が売主や買主のいずれにとっても円[…]